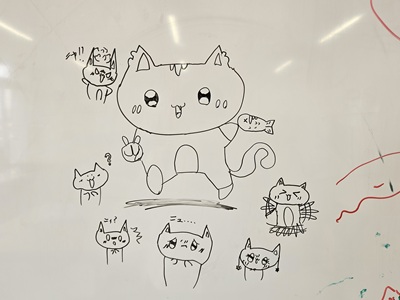トップページ
> とちぎ蔵の街自主夜間中学
> 第27回開催報告
2025.8.21
第27回(2025年8月17日)開催報告
全体報告
今回の報告は、「スリランカ大使館表敬訪問報告」と番外編を含め、1万字にも及ぶ大作となりました。最後まで読むのは大変かと思いますが、中身の濃い話が続くので、是非最後までお付き合いを!・・ということで、全体報告は簡潔に。朝の歌を歌うコーナーでは、「前を向いて歩こう」を久しぶりに歌いました。4年前のこの時期に最初の自主夜間中学を宇都宮に開校した時、校舎も校歌もないなかで、せめて仮の校歌をつくろうと思い、坂本九さんの「上を向いて歩こう」の替え歌として、自分が作詞したものです。すべての参加者が歌えるように、今日は途中までの歌詞を1つ1つゆっくり確認し、そのうえでメロディーをつけて合唱。改めて歌詞の素晴らしさに酔いしれた瞬間でした・・ある人が「楽しさも くやしさも かたる とちぎのここ」の「くやしさ」という言葉が特に良いですね、と言ってくれたことを思い出しました。ちなみに、歌のコーナーの音頭はTさんとTさんが、メロディー担当の自分もT、TTTコンビとなっています。
9月のビッグイベント(13日上映会、28日シンポジウム28)のチラシ裏面に「自主夜間中学とは」という短い文章を載せました。午前中の活動なのになぜ「夜間」という言葉を使うのかについて説明したものです。(田巻松雄)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは日曜日の午前中に「だれでも、いつからでも、いつまでも」無料で学べる教室を開いています。そして、この教室をとちぎ蔵の街自主(夜間中学と呼んでいます。昼間の教室なのに、なぜ夜間中学なのでしょうか。
現在、全国で62校の公立夜間中学が設置されています。公立夜間中学では年齢も国籍も多様な人々が学んで(まな)います。私たちは、公立夜間中学が実践しているような学習者一人一人の多様なニーズに寄り添い丁寧に応援する学びの場を市民の手でつくり育てたいと考えました。このような想いを込めて、自主夜間中学と呼んでいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小学生クラス
ジッケン! → 実演!!いろいろな液体を特殊な膜で、ろ過。できあがった液体の色・匂いの観察と理由考察、いよいよ完結編です。
教材は、前回にひきつづき、東レ無償貸与によるリバネス提供科学教育プログラム「中空糸膜」。
(教材の詳細は以下のリンクをご覧ください。)
https://ed.lne.st/2023/06/01/toray_kyozai2023/ (2023年度募集時のもの。)
*みなさん、これタダなんだし、使わせてもらわない手はないですよ。
小学3~5年生でも、考察までよくできました。
〈本日のメニュー〉 テーマ:「どうなる?」→「どうなった?」→「どうして?」
(1) 絵の具の色水(赤・青・黄)の、ろ過 *ひとり1色を担当。
(2) 食紅水溶液(赤・青・黄) の、ろ過 *ひとり1色を担当。
(3) ジュース(グレープ・オレンジ・コーラ) の、ろ過 *ひとり1飲料を担当。
(4) 実演 ①「どうなるでしょうか?」 ②「これ、もとは な~んだ?」
(1) 絵の具の色水
【予想】「変わらない」(2人)。/「変わる(透き通った水になる)」(2人)。
【実験・観察】赤・青・黄ぜんぶ透き通った水になりました。
【考察】使った膜は、「網の目」だったことをスタッフから説明。(※1)
(2) 食紅水溶液
【予想】「変わらない」(1人)。/「とうめいなみず」「色だけとれる」(3人)。
【実験・観察】もとの赤・青・黄色のままになりました。(※2)
【考察】・ざいりょうがちがうから。
・ぜんぶ まぜあって、ぜんぶ とおった。
・こながちいさいから、かわらなかった。
(3)①グレープジュース
【予想】色:ある、 におい:ある、 味:ある(※3)
【実験・観察】色:なし、 におい:ある、 味:ある
【考察】わからない
(3)②オレンジジュース
【予想】色:なくなる、 におい:すいこんでもにおいはある、 味:ある
【実験・観察】色:なくなった、 におい:あった、 味:すっごくあまくなった
【考察】色:そうめんのおかげで。(※4)、 におい:においは空気だから、ふつうに とおれる
(3)③コーラ(※5)
【予想】色:かわる、 におい:ある、 味:サイダーあじ
【実験・観察】色:とうめい、 におい:おなじ、 味:おなじ
【考察】味:コーラのなかは、たんさんが はいっているから たんさんになった
(4) 帰りの会で、全スタッフ・学習者に向けて「クイズ → 実演 → 答え合わせ+解説」をしてくれました。
①「どうなるでしょうか?」
絵の具の色水(青、黄)…Aちゃん姉妹、Sちゃん担当 / 食紅の水溶液(赤)…Aくん担当(※6)
みなさんに、膜を通った液体がどう変わるか、当ててもらいました。大人でもなかなか当たりませんね。
網の目を通れる小さい色のつぶと、通れない大きい色のつぶがあるというSちゃんの解説に、みなさんガッテンしたことでしょう。
②「これ、もとは な~んだ?」
つづきまして、ジュース(グレープ・オレンジ・コーラ) の、ろ過液に残る香りで、もとは何ジュースだったか当ててもらいました。みなさん、たいへん鼻が効くようで、全問正解でした。
(以下のエピソードは、上記の※印と突き合わせてお読みください。)
※1:エピソード1「救世主あらわる!」
当方の解説図が雑すぎて、子どもたち苦笑。満を持してSちゃんの登場です。華麗な描画と説明で、スタッフ・子どもたちからの尊敬の眼差しを、一身に集めていました。
※2:エピソード2「痛恨のミス」
食紅の色が中空糸膜を通過するのを確認した子どもたち。「食紅も透明にするにはどうすればいいの?」
ウン、ウン。いいぞいいぞ。探究っぽいね。「それにはまず、実験2の結果のわけを考えてみよっか?」というところまでは良かったんだけど、考察が終わったあとで、さっきの疑問に戻るのを忘れちゃった……。(ガックリ。)
水溶液(食紅)と、コロイド溶液(絵の具の色水)の違いも説明できるチャンスだったのに……。
※3:エピソード3「ハテ?『味の観察』とは異なことを。」
実験器具はすべてキレイに洗浄してありますが、実験中に液に雑菌や他の実験の異物が混ざっているかもしれません。よいこのみなさんは、決して口に入れてはいけません。(どうやって味を観察したかは部外秘です。)
※4:エピソード4「お昼はそうめん食べたい」
中空糸膜って、色も細さも夏の風物詩のアレにソックリ。使用後の、ほのかにピンクや黄色に染まってるあたり、ますますリアルさを醸し出しています。
食指を動かされたSちゃん、同行しているお母さんにリクエストです。
今後、当校での中空糸膜の愛称は「そうめん」に決定いたしました。
(子どもたちよ、よく聞きなさい。軽~く言っちゃうけど、夏にそうめん茹でるのは、地味に地獄なのですよ。クーラーついてないキッチンでは、ね。)
※5:エピソード5「探究は、大人の事情にお構いなしにつづく」
グレープジュース・オレンジジュース・コーラだけで終わるわけがないのが、子どもたちの探究心。
残り時間が気がかりなスタッフをよそに、手持ちのメロンジュース、レモンジュース、スポーツドリンクで、実験はつぎつぎと延長されてゆくのであった……。
※6:エピソード6 「食紅よ、お前もか!」
帰りの会でAくんが実演中のこと。色も通過するはずの食紅(赤)から、透明になった水がピストン内に登ってくる!
Aくん、おやっ?という顔。近くにいたスタッフからも「あれっ?」という声が漏れました。
その後、想定どおりに赤い液がゆっくりと上ってきました。実験って、1回そうなったから、いつもこうなる!ってものではありませんね。(これって、セレンディピティーだっ!)
未使用状態の中空糸膜に付着させているワセリンが、膜の性能を一時的に上げたのではないかと考えています。
(Y)
中高生クラス
〇17日の中高生クラスは中2と高1の二人が学習者でした。そこで、一時限目と二時限目を二人の支援者が各々の教科を支援する事にしました。私は1時限目は高1の生物を、2時限目は中2の数学を支援しました。いずれも教科を教える前に、教科書に出て来る漢字混じりの日本語文章の意味を教えねばなりませんでした。二人とも漢字を間違いながらも読めるのですが意味は解っていません。母語や英語にすると初めてわかります。ですから学校の授業では日本語は聞き取れますが意味が解らず、授業内容を殆ど把握できていないとのことです。
高1の生物は教科書を読み、まず日本語を理解したうえで、漢字混じりの教科用語を教えました。この専門用語的な教科用語をわかりやすい日本語で説明するのは至難の業です。中2の数学も問題文章の日本語を説明し何が問われているかを理解させねばなりません。それから、解き方を教えますが学習者に計算式を書かせながら解いていくのですが 時間がかかり、1時限で数問しか進めませんでした。
外国人二人の学校授業受講の様子を思うと我々が思う以上に苦労していると思われてなりません。(村田孝)
〇後半で担当したのは、参加してくれた高校1年生を対象とした「生物基礎」、特に遺伝の最初の部分でした。DNAについての細かな部分からはじまり、全体の構造、RNAとの違い、タンパク質のでき方などについて、教科書を見ながら順番に確認しました。教科書の表現も段々と複雑になり、「遺伝子の転写と翻訳」など、日本人でも「え? は?」となるような専門的な語句や表現が増えてきました。短時間でしたが、読み方や意味を確かめながら、「分かる範囲」を少しずつ広げていければと思います。(M)
社会人クラス
〇『蔵の街自主夜間中学も、開校から約10ヵ月が経ちました。毎回休まず参加する学習者、マイペースで来る学習者などなど、それぞれの生活に合わせて、なんとなくパターンが定着しつつある感があります。スタッフも同じで、それぞれの仕事や生活を送りつつ、それぞれのできる範囲で参加しています。僕も毎回参加とはいきませんので、ほぼ毎回違う学習者の学習のお手伝いをしています。今日は、初めて参加してくれた学習者を担当しました。最初に気をつけていることは、最初に教室に入る時にちゃんと寄り添って、できるだけアウェー感を感じさせないということです。今日の学習者さんも、最初は少し緊張していたようですが、すぐに馴染んでくれました。名前で呼ぶことはとても大切ですので、最初の日に必ずやることは、まず名札を作ります。しかし名前にもお国柄があり、外国籍の方の名前は日本人にとってとても覚えにくいのです(外国の方は日本人の名前について、同じように思っていることでしょうね)。そこで、他のスタッフにもわかりやすいように、呼びやすい名前を聞き、できるだけ大きく書いてもらいます。次に、スタッフの誰が担当しても困らないように、簡単なプロフィールと学習の目的(目標)を確認して情報ファイルとして共有しています。さらに、毎回の学習内容と使用したテキスト、次回の学習予定などをその日の担当者が記入することになっています。今日担当した方は、ネパールでも日本語の勉強をしっかりしてきたようで、日本語の基礎的なことは、ほぼ理解していましたので、聞き取りもスムーズにできました。彼は、僕に「まず日本語能力試験4級を取りたい」と話してくれました。僕たちも全力で応援していきたいです。(矢部昭仁)〇これまで何度もお顔は拝見していましたが、共に学習するのは初めての女性。ネパールから日本に来てまだ1年ほどとのことですが、明るくお話しをしている様子が記憶にあります。今回は同じ職場の同僚の男性を連れてきました。前回の指導はベテランの女性でしたので前回に引き続きN4のテキストを継続して用い勉強しました。彼女が用意してきたノートが2冊あり、ひとつは半分以上使用しているもので、日本語とネパール語の書き込みがびっしりされているもの。もう一冊は全く新しいもの。僕は使いかけの方を開こうと手に取ると、彼女は「こっちは家用です。新しいノートで」と言いました。なるほどそのつもりで用意してきたんだなと納得して、スタートです。
テキストの問題はいくつかありますが、日本語の例文の一部がカッコで空白になっており、そこに入る言葉を選ぶ形式の問題では、日本人の僕から見てもアレ?と感じるところもあり、外国の人がそれを理解するのは難しいだろうなと感じます。⚫︎大事なものは机の( )にしまいます。
正解は「引き出し」ですが、「押し入れ」や「棚」という設問もあります。押し入れという概念は外国人にはあるのだろうか?とか棚にも大事なものを置くこともあるかもと思ったり、全くネパール語が理解できない頼りない先生は手元にあるスマートフォンだけが頼みの綱です。でも、そのおかげで意思の疎通ができるということも事実で、正解である言葉以外もひとつひとつ検索してはその意味をネパール語で見たり、写真、動画の画面を見てもらいます。彼女はそれをひとつひとつ丁寧に書き写し、意味を自分の中に入れていきます。押し入れとは自分の部屋にもあるものをしまう場所だとか、棚とは壁などにあるものを置く場所であるということを知るのでしょう。また、「大事なもの」と「大切なもの」の意味の違いはなんだろうか?「ゆうべ」と「昨日の夜」はよくにているけど、日本語で「ジャズとワインの夕べ」とは言うけどこれが「ゆうべ」だとちょっとニュアンスが違うように感じる、それを彼女に分かるように伝えるのはどうしたら良いのか?「ジャズとワインの昨日の夜」とは言わないのはなぜか?と質問されたら答えられないなと思うのです。自由の反対語は不自由、便利な反対語は不便で、不便利とは言わない。言葉とは何だろうか?でもネパールから日本に来て一年ほどなのに話をして笑い合い、帰りのミーティングで、小学生の実験の報告を見ながら手を叩いて笑うのも言葉があるからこそなのだ。言葉は便利で時に不便だ。蔵の街夜間中学での時間は間違いなく僕自身が言葉や国や人について考える貴重な時間なのだと再認識する時間なのだ。(嶋田一雄)
〇 社会人の学習者は8人です。ネパール人4人、日本人1人、インド人1人、中国人1人、タイ人1人。11時過ぎに日本人の学習見学者がくる。スタッフは22名。
新しく来てくれた人はネパール人の20歳前半の若者。ネパールで3か月日本語を学んできたという。精悍な顔つきには、これから日本で頑張ろうという目力がジンジン伝わってきました。日本でどんな事を学びどんな仕事に就きたいのか、さらに、永住を考えているのかと若者から醸し出されるオーラに明るい希望のようなものが見えてきたように感じとることができました。
社会人クラスには彼のような20代の若者が来た事がなかったからより新鮮に映りました。社会人クラスは30代、40代が殆どです。日本の若者が失いかけてしまった前に進む力や、何でも吸収してやろうとする野望を彼に見る事ができた。
多分、あれだかの目力があればそんなに時間がかからなくても目的が達成できる気がする。ネパールから日本はどのように映っているのか知りたくなってきた。このところ、ネパール人が押し寄せてきているからだ。例えば、日本の高度成長期に若者が都会にあこがれて田舎を離れていったように、彼らも日本に夢を抱いて押し寄せて来るのかも知れない。来日して1番先に突き当たるのは言葉の壁ではないかと思う。言葉がわからなければ意思疎通をとることができないからだ。
彼は食品工場で働いてると言う。カタカナで会社名を書いてくらた。県内では大手食品メーカーだ。ひらがな、カタカナはゆっくりなら書けそうだ。時間がなかったのでこれ以上のことは窺うことはできなかった。
今回も、ネパール人のNさんの支援をするつもりでいたら、Tさんが「誰も支援する人がいないんです」と歩み寄ってきたので、2人で支援することになった。
Nさんは兄弟で続けて来ている。今回で5回目になる。ひらがなは書けるようになったが、カタカナはまだ頼りない。Tさん主導で支援する事になったので、傍らで見守る役に徹することになった。
20分遅れて、タイ人の女性がバックをかかえてやってきた。かなり焦っていたようで、教室を間違えたと思い込んで、隣の教室に入っていってしまった。慌てて呼びにいった。彼女も毎回、来てくれている。日曜日が休みと教えてくれた。
ネパールの男の人はTさんが支援することになり、彼女をバックアップすることになった。彼女はタイ式マッサージ店で働いてる。お客さんが我儘な要求をしてきた時に断る言葉を教えてくださいと口にしてきた。
ある日、マッサージ店に行きたいので自宅まで迎に来てほしいと強い口調でかかってきたという。その時は、「ダメです」と同じように強い言葉で突き放したようです。そんな時には、どんな言葉で断ったらと、真剣に訴えてきました。「ダメですでは、あまりにストレート過ぎてお客さんを怒らせてしまうからもう少し丁寧に断った方が、いいですね」
「どんなふうに断れば良いのですか」「申し訳ありませんが、当店では送り迎えのサービスは行っていないのでよろしくお願いしますと、優しく言えばお客さんも悪い気がしないのではと思います」と言うと、日本語ではなくタイ語でノートに書き始めた。どうして日本語で書かないのかなと思ったが、口には出すことができなかった。来日して、20年になるという。20年経っても日本語が書けないというのは、多分、日本語で書いたり読んだりする必要がなかったからではと深読みをしてみた。会話は何とかできるが書いたり読んだりすることは学ばなければできないことに気づき自主夜間中学に来るようになったのではと更に深読みする。
タイ人の女性と結婚した友人の自宅に訪ねて行った事があった。タイ料理をご馳走になったがあまりの辛さに、どんな物を食べたのか記憶が飛んでしまった。スープをのんだ気がしたが全て辛かった。彼女は20年日本で暮らしているので、口がすっかり日本食になってしまったと笑う。辛いものは食べられないとハッキリ口にする。1番の好物は蕎麦という。その他にすし、ラーメンとすっかり日本料理が大好きになったとか。
突然、漢字を覚えたいと言い出した。「漢字はどのくらいあるの」と踏み込んできた。
「小学生で習う漢字は1000字くらいあるんじゃないの」「1000字もあるの」
「中学生になるとさらに増えるから、覚えるのが大変なんだよ。日本人も覚えるのに苦労してるんだよ。一気に覚えようとしても無理だから、毎回、一字一字ずつ覚えるようにすればマスターできるようになるから」と、慰めるがあまり納得してもらえなかった。
「学習の学は、読み方がふた通りあるんだよ。書き順もあるから覚えないと」と「学」の字を書こうとしたら、自信がなくなってしまった。書き順を覚えてないからだ。スマホで書き順を検索したらやはり間違えていたのに気づいた。更に、7画だと信じていたら、8画あった。教えてるつもりでも学んでいるのだと自覚した。彼女はまるで習字を書くように一字一字丁寧に書いていった。整った綺麗な字だった。今迄は、仕事と子育てで学ぶ余裕がなかったのでこれからは定時制に通い学びたいと口にした。
11時過ぎに大柄な男の人が、教室に入って来た。年齢は60歳半ばに見えた。若しかしたらもう少し上かもしれない。教室内をゆっくり回りながら学習の様子を覗きこんでいた。気になり声をかけてみた。「見学ですか」「ハイ、どんなことをやっているのか見にきたんです」。大柄な体には似合わず円やか声が返ってきた。本当に人は見かけだけでは判断できないと改めて思った。「ここの教室は学びたい人は誰でも学ぶことができるんです。どうぞ、来て下さい」。「私は、一応、中学は卒業したんですが、殆ど勉強はしてこなかったんです。だから、もう一度学びたいと思ってるんです」。「それなら、是非来てください」と、ノートに名前を書いてもらった。素直に書いてくれたので、本当に学びたいのだと受け止めた。久しぶりに日本人がきてくれたのでほんわか嬉しさがこみ上げてきた。
中味の濃い2時間があっという間に過ぎてしまった。満たされた時間だった。教室を出ようとしたらインド人のkさんが手を差し出してきたので握手をした。彼とは、全体のミーティングの教室で必ず、握手を交わしていた。今日は交わすことができなかったので握手を求めてきたのではと理解をした。彼は休みなく通っている。(国母仁)
スリランカ大使館表敬訪問報告
2025年8月18日(月)午後3時に、とちぎに夜間中学をつくり育てる会役員3名が、東京都港区高輪にあるスリランカ大使館を表敬訪問しましたので、ご報告します。今回の主な訪問目的は、「2024年度 世界の人々のためのJICA基金活用事業」の支援を受けて2024年12月20日に発行した『中学教科単語帳』(日本語⇒シンハラ語)を大使館に寄贈し、単語帳の普及や活用などについて意見交換するというものでした。
応対・面談してくださった大使館の主な方々は、ピヴィトゥル駐日スリランカ次期大使様、ティリニ参事官様、日本人職員の方の3名で大変友好的に迎えていただきました。つくり育てる会からは、副代表の仲田さん、会計の鄭さん、事務局長の佐々木の3名が出席しました。面談はすべて英語で活発に行われ、時間も40分以上にわたり、とても有意義で実りの多い訪問となりました。以下に面談内容の要点を記します。
まず、今回の表敬訪問を承諾してくださったことへのお礼を述べ、名刺交換も行いました。そのあと、持参した『中学教科単語帳』(日本語⇒シンハラ語)を次期大使と参事官にお渡しして、単語帳の特徴を地理の「いど(緯度)」を例にして、シンハラ語の単語にどう対応するかを説明しました。時にはシンハラ語の単語では収まらない記述が必要な場合もある点にも触れ、次期大使は関心を示されました。さらに追加贈呈の申し出も喜ばれていました。国際理解と交流のよい広がりができたのではないかと思います。
また、仲田さんが、本単語帳発行記念第1回交流会(昨年12月22日にきららの杜とちぎ蔵の街楽習館で開催)のチラシを次期大使に渡したことがきっかけとなり、今月30日(土)に第2回交流会が宇都宮で開かれることに話が及びました。このことを受け、鄭さんは第2回交流会に登壇するスリランカの人たちの紹介もしました。夜間中学で継続的に学習している社会人、多様な学び場での応援が実り高校に進学した人などです。進学者は成功事例ですねと次期大使は言って微笑みました。さらに本単語帳の作成に尽力した人たちもいます。
こうした交流会に関するやりとりが進む中で、次期大使は第2回交流会に関心を示し、参加の可能性を探っていただけることになりました。実現を切に願っています。
なお、上述した単語帳がJICA基金活用事業の支援を受けて出版されたこと、まもなくJICA筑波HPなどからダウンロードできるようになること、次はウルドゥー語単語帳が発行予定であることも伝えました。さらに、今回の表敬訪問報告を栃木市国際交流協会HPやJICA筑波HPに掲載することも承諾いただきました。最後に、次期大使自身のご提案により記念写真を撮ることもできました。日本人職員の方が撮影してくださり、次期大使と国旗を中心に、左側に参事官と鄭さんが、右側に仲田さんと私が写っています。
末筆ながら、今回の訪問を発案した「つくり育てる会」代表田巻さん、温かく受け入れてくださった大使館の皆様、面談で積極的に発言してくれた仲田さんと鄭さんなど、関係するすべての方々に心より感謝申し上げます。(佐々木一隆)
(番外編) サイコドラマ体験会
「サイコドラマ」は、即興劇を使った集団心理療法です。スタッフFさんは14年来、学会や研修グループに参加して研鑽を続けてきているとのこと。これをシェアしてもらわないのは、もったいなさすぎる!というわけで、蔵の街校 終了後の12:35~13:10にかけて、好奇心旺盛な5人がFさんとサイコドラマを体験しました。お昼前だったこともあり、ウォームアップのエクササイズは「いま食べたいものを動作で伝える」。
先発のNさんの「そば(そうめん)」は明快でした。Kさんは「うなぎ」を表現するために焼くさまから演じていました。Y.K.さんの「梅おろしうどん」、すっぱさを表現した表情が参加者にウケていました。
つづいて、〈ロールリバース〉という、役割を交代しながらの場面再現。
Nさんがアラスカン・キング クラブを現地で食べた50年前のシーンに、みんなでタイムスリップしました。
1ドル=300円時代に、時価30ドルで食べたタラバガニの脚は、バターのようだったといいます。
Nさんの実演のあと、本人役、同席の同僚役、ウエイター役、と、次々に登場人物を増やしながら、ときに、同僚役が本人役を演じたりして、物語を先に進めていきます。
みなさん、登場人物になりきって、自分の中に他人の視点をつくっていっていたようです。
「こういうの、また開くのもいいよね。」という感想も出ましたので、今回の機を逃した方は、次回に乞うご期待。(Y)